
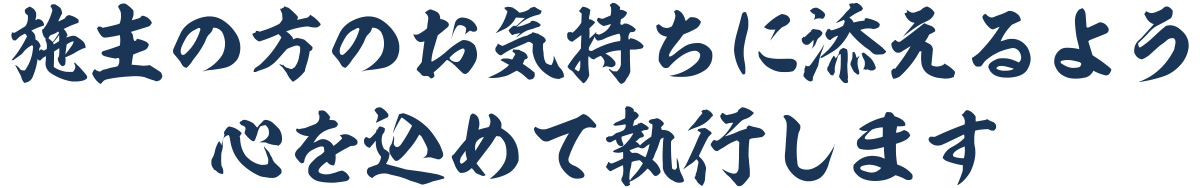
葬儀関連の法要には、臨終勤行(りんじゅうごんぎょう)、(納棺勤行)(のうかんごんぎょう)、通夜勤行(つやごんぎょう)、(出棺勤行)(しゅっかんごんぎょう)、葬場勤行(そうじょうごんぎょう)、火屋勤行(ひやごんぎょう)、収骨勤行(しゅうこつごんぎょう)、還骨勤行(かんこつごんぎょう)という流れがあります。
・葬儀には六曜の友引を避けるというようなお日柄を選ぶ風習が根強く残っていますが、浄土真宗では迷信として退けます。
その後、御命日から七日毎に初七日(しょなのか)、二七日(ふたなのか)、・・・とお勤めし七七日を満中陰(まんちゅういん)として所謂四十九日(しじゅうくにち)法要を営みます。
・仏教では、中陰とは人の死から仏の誕生(成仏)に至る謂わば猶予期間と捉えます。イメージとすれば、遺族は追善(ついぜん)の法要を重ね、その功徳で故人の成仏の後押しをするということでしょうか。
ただ浄土真宗では、往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)の教義ですし故人の往生・成仏は偏(ひとえ)に阿弥陀如来の独用(ひとりばたらき)に依るのですから、追善の必要は全くありません。中陰の間を、遺族自らがお勤めのご縁に遇(あ)い、個人を偲びながらお別れの悲しみから徐々に癒されていく期間と受け止めます。
・大切な方とのお別れには、どうしても死への怖(おそ)れが付きまといます。また潔斎(けっさい)という日本独特の精神風土からは血を忌(い)み嫌う習俗が色濃く残存します。
先に述べました友引についても元は同じなのですが、浄土真宗では、かつて「門徒もの知らず」(物忌(ものい)み知らず)と他宗の信者から揶揄(やゆ)されたように、死や血から距離を置き潔斎など身を徒(いたずら)に清らかに保つ囚(とら)われからは絶対的に解放されていました。これは、「念仏者は無碍(むげ)の一道(いちどう)」と示された親鸞聖人のお導きにより、お念仏とともに現世を怖れなく生きる浄土真宗の門徒の寧(むし)ろ矜持(きょうじ)と言えましょう。
満中陰にも三月越(みつきご)しを避けるという伝承があるのですが、これも「四十九が三月(しじゅうくがみにつく)」を「始終苦が身に付く」と読み替えた語呂合わせにしか過ぎません。これも死を怖れる気持ちの裏返しと考えられます。
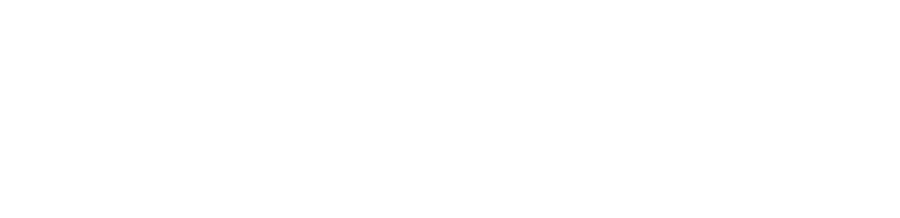

よく「いつ納骨をすれば良いのか」というお訊ねをいただきます。「こうあらねば」的な約束事はありませんのでいくつかのケースを挙げておきます。
①満中陰法要の後
②春秋の彼岸やお盆の時期に合わせて
③いきなり淋しいので1~2年手元に置いておきたいというお気持ちも否定しません
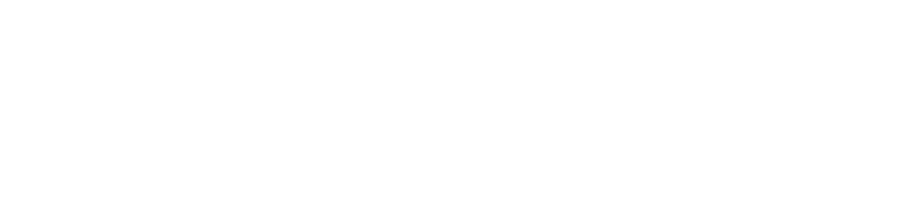

浄土真宗では一周忌(いっしゅうき)、三回忌(満二年 以下同)、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十五回忌、三十三回忌、五十回忌、百回忌をお勤めします。仏教情報誌などに書かれている二十三回忌、二十七回忌、三十七回忌はありません。
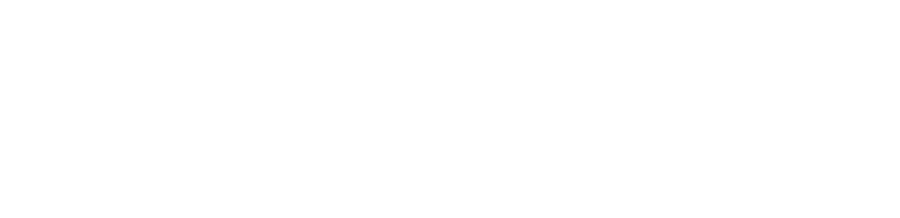

ご家庭にみ仏さまをお迎えするお慶びの法要です。赤いローソク(朱蝋)に灯(ともしび)を点(とも)し結ばれた仏縁を感謝します。灯は阿弥陀如来の智慧の明るさと慈悲の温もりを表します。
その他慶びの法要として、仏前結婚式や初参式(しょさんしき)(新生児の寺参り)などがあります。
また随時個別のご相談を承りますのでご遠慮なくお申し出ください。
© senkyouji プライバシーポリシー